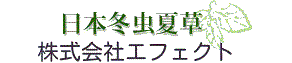◆肝がん(肝癌,肝臓癌,肝臓癌,肝細胞癌,肝内胆管癌)
肝臓がん(肝臓癌)は肝臓に発生するがんの総称であり、主に肝細胞がんと胆管がんがあり、その殆どは肝細胞がんです。
胆管がんには肝内胆管がんと肝外胆管がんがあり、通常は胆管がんとは肝外胆管がんを指しており、肝内胆管がんは肝臓がんとして扱われます。
肝臓がんには肝臓を原発巣とする原発性肝がんと胃や大腸などから肝臓に転移した転移性肝臓がんがあり、治療方法も異なります。
肝臓がんの原因
原発性肝細胞がんのおよそ9割はB型肝炎、C型肝炎ウイルス感染症による急性肝炎が原因になっており、全体の7割近くはウィルス性肝炎のための肝硬変を合併することになります。
このため肝炎ウイルスに陽性の方は定期的な経過観察が必要であるといえます。
アルコール性肝炎から肝硬変になった場合に肝臓がんが発症する率は低いですが、日常的にアルコールの摂取量が多い方がウイルス性肝炎になった場合は高い確率で肝臓がんが発生します。
急性肝炎から肝硬変や肝臓がんに移行する際には、血小板の数値が低くなる傾向があるため、肝炎ウイルスをお持ちの方で健康診断などで血小板の数値が低い方は注意が必要です。
肝臓がんは再発率が極めて高いがんであり、難治性の経過をたどることが多く5年生存率もかなり低い率に留まります。
肝臓がんの症状
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほどがんの病期が進むまで特有の症状がないため症状が深刻化しやすいです。
肝炎や肝硬変などの併発しやすい病気の症状からがん発覚に至るケースも多いです。
症状が進行すると手足や顔、白目の部分が黄色くなる「黄疸」や肝臓の腫れにより血管をが圧迫されることで静脈がこぶのように大きく膨らむ静脈瘤ができることがあります。
進行した肝臓がんでは血液が脾臓に流れ込むことで赤血球が壊され「貧血」になることもあります。
貧血になるとめまいや冷や汗、脱力感などの症状が出ます。
肝臓に血液を運ぶ血管のうち門脈が詰まると、小腸や大腸に血液が溜まり、腸がむくんでしまうことで「便秘や下痢」が続くことがあります。
更に大きくなった肝がんが破裂して「腹痛」を起こすこともあります。
みぞおち辺りにグリグリとしたシコリが現れることもあります。
肝臓がんは気付いた時に症状が進行していることが多いため、日頃から良質なたんぱく質を取り、ビタミン、ミネラルが多い栄養バランスのとれた食事を行って肝臓を労わることが大切です。
アルコールや糖質、脂質の取りすぎに注意して、化学薬品(合成着色料、保存料、食品添加物、農薬、防腐剤、医薬品等) の摂取をできるだけ控えることが大切です。
肝内胆管がんの場合も早期に確認できる症状は特にありません。
肝内胆管がんは浸潤性の強いがんのため胆管に染み込むように拡がって閉塞させ、黄疸が起きます。
肝内胆管がんは非常に見つかりにくいがんであるため、発見時点で症状が進行している場合が多いがんです。
肝機能の低下が進むと、血管やリンパ管から漏れ出した成分が腹部に溜まる「腹水」という状態になる場合があります。
肝臓がんの診断
肝臓がんの診断は難しいため、血液検査と画像診断法が両方行われます。
これらの検査で肝臓がんと判断しきれない場合は、針生検という肝臓の腫瘍部分に針を刺して少量の組織片を顕微鏡で調べる検査も行われます。
肝臓がんの血液検査
肝臓がんの検査に使用される血液検査と基準値を示します。
基準値は施設によって異なる場合があります。
肝機能に異常がないかを調べるために血液中のGOT(AST)とGPT(ALT)の値を調べます。
これらは肝細胞に含まれている酵素で、肝細胞が壊されると血液中に大量に流れ込むため数値が上昇します。
肝細胞がどの程度障害を受けているのかの指標になります。
血小板は血液を固めるために必要な血球成分です。
肝硬変になると血液の中の血小板が減少していき10万/ul以下に低下すると肝臓がんの発症率が高くなります。
アルブミンは血液蛋白の一部で肝臓でしか作られないため肝機能が低下してくるとアルブミンの数値も低下します。
アルブミンが著しく少なくなると腹水や浮腫みの症状がでます。
肝細胞に障害がある場合に上昇する数値で、総ビリルビンが増えると黄疸になります。
肝細胞がんのおよそ90%で陽性になる腫瘍マーカーです。
元来は胎児の肝臓と卵黄嚢で産生される糖タンパクで出生後には急速に低下しますが、肝癌になるとこのタンパク質の合成が活発になります。
PIVKA-IIは肝細胞がんに特有の腫瘍マーカーで他の疾患では上昇することは殆どありません。
ビタミンKの欠乏時やワーファリン薬を服用しているときにも上昇することがあります。
肝臓がんの画像検査
肝臓がんを早期に発見するうえで有効な検査になります。
超音波診断装置を使用する検査で、直径が1-2cm程度の小さな肝がんでも見つける事ができる確率が高く一般にも普及している検査です。
CT検査はX線によって体内の詳細な画像を連続的に撮影することで鮮明な画像を得ることができ、正確で詳細な診断を行うことができます。
他臓器やリンパ節転移の有無を調べることができ、進行状況を調べる上で重要な検査になります。
MRI検査はCTとは違い磁場を使って体内の詳細な画像を連続的に撮影する検査です。
放射線の被曝がなく超音波検査では見分けの付きにくいがんもMRI検査で診断できる場合があります。
足の付け根かの動脈からカテーテルと呼ばれる細い管を肝臓まで挿入し、造影剤を注入してエックス線撮影を行う検査です。
超音波検査の画像で肝臓がんの位置を確認しながら、体表から細い針を刺してがん細胞の一部を採取し顕微鏡で詳しく検査する方法です。
肝生検はがん細胞が針を刺した際に散ってしまう危険性があるため、血液検査や画像検査で診断が付かなかった場合に行われます。
肝臓がんの治療
肝臓がんの治療は、がんの進み具合、患者さんの年齢・体力、肝機能の状態、合併症の有無などから判断して治療法が選択されます。
肝臓がん治療の中心は外科療法、肝動脈塞栓術、エタノール注入療法などです。
他にマイクロ波凝固療法、ラジオ波凝固療法、凍結療法、化学療法(抗がん剤)などを行う場合があります。
肝臓は再生能力のとても高い臓器で、健康な肝臓は70%近くが切除されてもほぼ元通りに再生するため、基本的には外科手術によってがんを含む肝臓を切除する方法が取られます。
ですが、慢性肝炎や肝硬変などによって肝機能が低下している場合は再生力が低下するため、切除が行えない場合は移植や手術以外の方法が選択されることになります。
肝臓に放射線を照射すると肝機能が損なわれ、がん化する恐れもあるため骨に転移した場合を除いて放射線療法はあまり行われません。
ただし、陽子線や重粒子線をつかった照射範囲を限定できる放射線治療は肝臓がんに有効性が示唆されています。
肝臓がんの病期分類
肝臓がんの病期は下記のがんの大きさや浸潤、転移数、血管への広がり具合によって分類されます
条件1.がんの大きさが直径2cmを超えている
条件2.がんが2つ以上ある
条件3.がんが血管の中に拡がっている
| Ⅰ期 |
3つの条件に1つも当てはまらない場合 |
|---|---|
| Ⅱ期 |
3つの条件のうち1つに当てはまる場合 |
| Ⅲ期 |
3つの条件のうち2つに当てはまる場合 |
| Ⅳa期 |
3つの条件全てに当てはまるがリンパ節や多臓器への転移がない |
| Ⅳb期 |
3つの条件に関係なく遠隔臓器への転移がある場合 |
肝臓がんの外科手術
肝切除は肝臓の一部を切り取る手術で、最大の利点はがんが治る可能性がもっとも高いということです。
デメリットは合併症が起こる場合が少なからずあり、おそよ1~2%が手術に起因して死に至ります。
また入院期間が1~2ヶ月、退院してからの自宅療養が1~2ヶ月程必要となり療養が長期に及ぶことがあげられます。
肝臓はひとかたまりの臓器ですが、肝臓内を走る血管の分布によっていくつかの区画に分けて考えられます。
まず左葉と右葉の二つに分かれており、更に左葉は外側区域と内側区域、右葉は前区域と後区域に分かれます。
さらに外側区域、前区域、後区域はさらに上下2つの亜区域に分かれ、これに内側区域と尾状葉(肝臓の後ろ側の小部分)を加えて合計8つの亜区域に分かれます。
肝臓の切り取り方は、これら肝の区画の「どこ」を「どのくらい」切除するかによって表現されます。
区域をまたいでいる場合には複数の区域を切除します。
肝機能が低下していて大きく切除できない場合は、亜区域切除や部分切除などより肝臓をできるだけ残して小さく切除します。
肝臓がんは再発の非常に多いがんで、肝切除術によってがん細胞を切除したとしても3~5年後までに再発する確立は70%に達します。
再発した場合は条件が整っていれば再手術することができ、その他にも下記のような治療方法があります。
肝動脈塞栓術(TAE)
肝臓は肝動脈と門脈という二つの血管から酸素や栄養分を受けていますが、一方で肝臓がんは肝動脈のみから栄養の供給を受けています。
肝動脈塞栓療法はこの性質を利用して肝臓がんに栄養を送っている肝動脈を塞いで、がん細胞へ酸素や栄養を供給されないようにすることで壊死させる治療方法です。
肝動脈塞栓術は1回の治療で1週間ほどの入院が必要です。
具体的には太ももの付け根の部分からカテーテルと呼ばれる管を肝動脈まで挿入し、抗がん剤をしみこませた「ゼラチン・スポンジ」という小さなスポンジ状のゼラチンを詰めて肝動脈を詰まらせます。
肝動脈が詰まっているためがんは酸素などの供給を受けることができなくなり壊死します。
その後スポンジは自然に溶けて血流は元通りに回復します。
肝動脈塞栓術は、肝臓がんが進行して完全に切除できないと判断された場合や、肝臓の状態が悪く手術できないと判断された場合に行われる治療方法です。
肝動脈塞栓術はがんの進み具合による制限はなく適応範囲が広い治療ですが、がん細胞が門脈を塞いでいる場合や黄疸や腹水が見られるほど肝機能が低下している場合は行うことができません。
治療後1週間程は発熱がみられたり、食欲不振や腹痛、吐き気などの副作用が現れる場合があります。
肝動脈塞栓術は他の治療方法に比べて長所が多く、適応の制限も少ないため最近の肝臓がん延命期間の向上に最も寄与しています。
しかし、完全に治りきる確率(完全治癒率)は現在のところ10%程度です。
経皮的エタノール注入療法
経皮的エタノール注入療法とは超音波画像で確認したがん細胞の位置をに100%エタノール、すなわち純アルコールを肝臓がんの部分へ注射して化学作用によりがん組織を死滅させる治療方法です。
エタノールにはタンパク質を凝固させる作用があり、エタノールを注入された細胞は瞬時に固まって壊死します。
問題点としては体内の直接見えない部分にあるがん細胞の位置把握が難しく、正常な肝細胞を巻き込んで肝臓機能に悪影響を及ぼす可能性があることです。
一般的には肝機能が一定以上で、がんの直径が3cm以下かつ3個以下の場合が経皮的エタノール注入療法の対象とされています。
がん細胞の大きさが2cmを超えるとアルコールとの接触が完全に行うことができないケースが増えて治療成績が落ちます。
エタノール注入療法はがんの大きさや個数に応じて複数回の治療を行うことになります。
副作用は塞栓術に比べて軽微で3-4日毎に治療を行うことができます。
マイクロ波凝固療法、ラジオ波凝固療法
マイクロ波凝固療法は、電子レンジにも使われているマイクロ波を利用してがんを焼いて殺す治療方法です。
電子レンジはマイクロ波を使って水分子を振動させ食べ物を加熱しますが、この治療法では体表から長い針を刺し、針の先からマイクロ波を出します。
この療法の問題点は、とても高熱になるということです。
そのため正常な組織も焼かれてしまう可能性が高く、肝臓の周りの臓器までも傷ついてしまう危険性があります。
また、マイクロ波ではなくラジオ波を使ってがんを焼いて殺すラジオ波凝固療法もあります。
ラジオ波はマイクロ波と比べて温度が高くならず正常な細胞を焼く可能性を下げながら、小さながん細胞を焼くことができます。
放射線療法
放射線療法は放射線を使ってがん細胞を殺す治療方法です。
日本では肝臓がんの場合、放射線療法はあまり行われていません。
一部肝臓癌が骨に転移した場合には痛みの症状を緩和する目的で行われることがあります。
局所化学療法(動注抗がん剤)
動注抗がん剤はここ数年の間に普及し始めた治療方法で、太ももの付け根の部分からカテーテルと呼ばれる管を肝動脈まで挿入し、肝動脈から抗がん剤を注入する方法です。
一度の注入だけでは効果があまり効果が望めない場合には、手術で開腹して直接肝動脈にカテーテルを挿入するか、足のつけ根の動脈(大腿動脈の枝)からカテーテルを肝動脈まで進めるか、どちらかの方法でカテーテルを留置して、腹部の皮膚下に埋め込んだ、薬液注入用の小さい貯留容器(リザーバーまたはポートと呼びます)から抗がん剤を注入します。
新しい治療方法であるため、現在のところどの程度効果が期待できるのか分かっていないのが現状であり、肝動脈塞栓術やエタノール注入などができない場合に次善の策として行われています。
肝臓がんの化学療法に使われる抗がん剤はマイトマイシンC、5-FU、シスプラチン(他にランダ、ブリプラチン)、アドリアマイシン、ファルモルビシン、ノバントロンなどが使われます。
放射線療法や抗がん剤を用いた化学療法では白血球減少による免疫力の低下が起こりやすいため体を清潔に保ち、規則正しい生活を送って免疫力を賦活させることが大切です。
肝内胆管がんの治療
肝内胆管がんの場合、外科的手術による切除以外有効な治療法はありません。
抗がん剤が使われることがありますが、効果はあまり望めません。
大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、膵臓がんなどを含む多くの臓器から肝臓には転移します。
肝臓に転移したがんを転移性肝臓がんといいます。
転移性肝臓がんの治療として最も確率の良いものは外科的手術になります。
しかし、転移性肝臓がんで手術が適応となるのは全身状態が手術に耐えられること、手術により肝臓にあるがんが取り除くことができること、原発巣(転移してきたがん)と肝臓以外にがんがないことなどが条件となります。
肝臓に転移した場合の多くは、がんが進行していて手術ができない場合も少なくありません。
大腸がんの肝転移の場合には比較的手術ができることが多く、良好な結果を得られる場合も少なくありません。胃がんや乳がんでは一部の方で手術が、肺がんや膵臓がんではほとんど適応になることはありません。
手術ができない場合は抗がん剤を肝動注または点滴で静脈投与することになります。
転移性肝臓がんは、原発部位の性質を引き継いでいるので使用する抗がん剤の種類も元のがんに応じて選択されます。
一時的に抗がん剤が有効な例もありますが、手術以外の方法で根治させることは困難です。
肝臓がんの有力な治療法である肝動脈塞栓療法(TAE)とエタノール注入療法(PEI)は転移性肝がんでは残念ながらあまり有効ではなく、これらの治療を行うことは稀です。